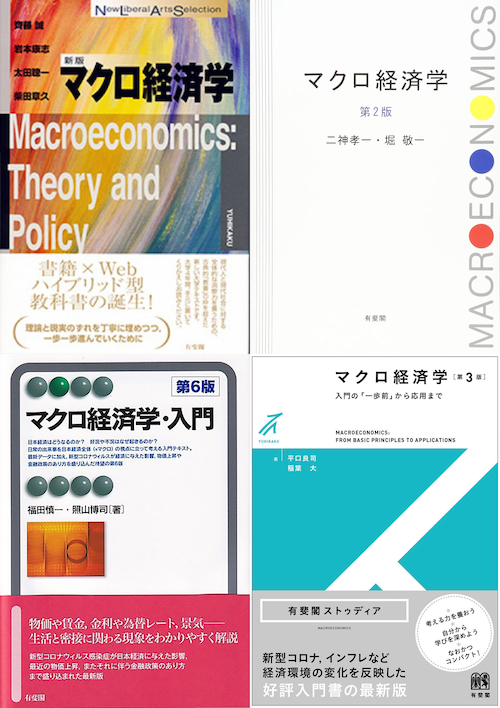東京大学で行われるマクロ経済学の授業,教科書(駒場:入門,本郷:経済学部,研究科)
【マクロ経済学入門,大学での最初でのおすすめランキング教科書,本】も確認する
東京大学でのマクロ経済学の授業、教科書概要
東大のマクロ経済学は「入門 → 中級(学部) → 上級/大学院コア → 大学院の発展・研究実践」という流れで積み上がる設計になっています。最初は教養学部、その後経済学部、経済学研究科での主要な授業を確認します。
もちろん他学部等でも行われていますが、経済学部・経済学研究科を中心に説明します。
大枠の流れ(学年が進むにつれて)
① 入門(教養・前期課程)
- 経済Ⅰ(Introduction to Economics):ミクロとマクロの基礎をセットで学ぶ。マクロ側は GDP、資産市場、IS–LM、AD–AS といった最初の道具立てを固める段階。講義ノートはUTOLに掲載、期末試験で評価。
② 中級(学部専門:2〜3年目想定)
- マクロ経済学Ⅰ(学部):マクロの体系を概説。GDPと物価、古典派(財・サービス市場・貨幣・労働・開放経済)、ソロー型の成長、景気循環(AD–AS/IS–LM、安定化政策、開放経済、フィリップス曲線)など。教科書はマンキュー等。日本語。
- マクロ経済学Ⅱ(学部):Ⅰの続きとして、消費・貯蓄、競争と厚生、成長と環境、財政政策、人口動態と社会保障にフォーカス。日本語。
③ 上級(学部上級)/大学院コア(修士1年想定)
ここは「学部上級」と「大学院科目」が内容・担当ともに対応しており、同じ授業を学部生と院生が一緒に履修するイメージです(後述の“名称違い=同一”ペア参照)。いずれも英語で開講。
- (上級/院)マクロ経済学Ⅰ:現代的な動学マクロの“道具”を横断的に学び、成長・景気循環・インフレ決定、金融市場・信用摩擦、金融政策やマクロプルーデンス政策まで広く扱う。期末試験中心。英語。
- (上級/院)マクロ経済学Ⅱ:一般均衡に基づく動学マクロの解析を本格化。動学計画法の理論と実装、RBC、サーチ&マッチング、資産価格、不完全市場、企業ダイナミクスなどへ展開(Macro I を必須とはしない設計)。宿題と試験。英語。
④ 大学院の発展・研究実践(修士〜博士段階)
- Macroeconomics based on Micro data:近年のマクロにおけるミクロデータ活用(HANK、分布・異質性、計算手法)を理論・実証の代表的論文で学ぶ。計算技法(異質的主体モデルの解法)も扱う。英語。
- マクロ経済学ワークショップ I / II:外部講演者による最先端研究のセミナー。参加とペーパー要約レポート等で評価。研究動向のキャッチアップやリサーチの“目”を養う位置づけ。英語。
学部4年生と修士1年目にやるコア授業は学部と院で名前が違いますが同等の授業です。
- 上級マクロ経済学Ⅰ(学部) ↔ マクロ経済学Ⅰ(大学院)
内容説明が実質同一(現代動学マクロの道具を使って成長・景気・インフレ・金融・政策を扱う)。英語。学部生と院生が一緒に学ぶ想定。 - 上級マクロ経済学Ⅱ(学部) ↔ マクロ経済学Ⅱ(大学院)
動学計画法〜RBC/不完全市場/企業ダイナミクス等まで踏み込む高度編。英語。Macro I を前提にしない設計(受講上フレキシブル)。
ざっくり学びの段階感
- 基礎を固める(入門):記述的な枠組み(IS–LM/AD–AS)と用語・指標のリテラシーを獲得。
- 道具を増やす(中級):古典派・成長・景気循環の標準理論を俯瞰し、政策論点(財政・人口・環境)に応用。
- 数理・計算に踏み込む(上級/院コア):動学計画法と一般均衡ベースの厳密な解析、実装・演習、資産価格や不完全市場へ。
- 最前線に接続(院発展):ミクロデータ/HANKなど最新手法を学び、ワークショップで現場の研究に触れて自分のテーマへ橋渡し。
となります。この他に学部、院ともにゼミなど所属があります。
東大の授業で使われるマクロ経済学の教科書、参考書
| 段階 | 科目(学部/院) | 教科書,参考書,主要論文 |
| 入門 | 経済Ⅰ(教養) | (指定なし) |
| その他マクロ経済学の入門など | ||
| 中級 | マクロ経済学Ⅰ(学部)/ マクロ経済学Ⅱ(学部) |
マンキュー『マクロ経済学 I』 |
| マンキュー『マクロ経済学 II』 | ||
| アセモグル=レイブソン=リスト『マクロ経済学』 | ||
| 宮尾龍蔵『マクロ経済学』 | ||
| 日本経済新聞 | ||
| The Wall Street Journal | ||
| The Economist | ||
| 上級/院コア | 上級マクロ経済学Ⅰ(学部)/ マクロ経済学Ⅰ(大学院) |
Ljungqvist & Sargent Recursive Macroeconomic Theory |
| Walsh Monetary Theory and Policy | ||
| 上級/院コア | 上級マクロ経済学Ⅱ(学部)/ マクロ経済学Ⅱ(大学院) |
Ljungqvist & Sargent Recursive Macroeconomic Theory |
| Stokey & Lucas with Prescott Recursive Methods in Economic Dynamics | ||
| 発展 | Macroeconomics based on Micro data (大学院) |
論文講読中心 |
| Autor, Dorn, Hanson (2013) | ||
| Achdou, Han, Lasry, Lions, Moll (2022) | ||
| Auclert, Rognlie, Straub (2021) | ||
| Kaplan, Moll, Violante (2018) | ||
| Baqaee, Farhi (2020) | ||
| Amiti, Itskhoki, Konings (2019) | ||
| Dávila, Schaab (2022) | ||
| 発展 | マクロ経済学ワークショップ I / II(大学院) |
N/A(各回の関連ペーパーを適宜) |
各テキストは、学習段階ごとに役割がはっきり分かれています。まず、マンキュー『マクロ経済学 I』『II』は学部中級向けの“土台づくり”に最適です。I では景気変動と短期分析(IS–LM、AD–AS、失業・インフレ、財政・金融政策)が中心で、経済の動きを直観的に捉える訓練になります。II は長期成長や制度・人口・財政などの“構造”に踏み込み、ソロー型成長や貯蓄・消費の理論、社会保障や環境といった政策論点まで扱います。いずれも数式は最小限で、実例やデータの図表が多く、抽象モデルと現実の橋渡しをしてくれる入門〜中級の定番です。
アセモグル=レイブソン=リスト『マクロ経済学』は、同じ学部中級でも“データで考える”色が濃い教科書です。自然実験や最新の実証研究をふまえ、ミクロの行動や制度の違いがマクロの結果にどう現れるかを重視します。格差・技術・制度・政策評価など現代的テーマを多く扱うため、理論の骨格をエビデンスで点検する姿勢を身につけるのに向いています。
宮尾龍蔵『マクロ経済学』は、日本語でしっかりと数理に触れたい学部中級〜上級入口の学習者に向きます。モデルの前提→均衡→比較静学/動学という“運用手順”を丁寧に追い、動学的一般均衡、RBC 系やニューケインジアンの政策分析まで視野に入ります。英語教科書に出てくる記法や考え方を日本語で整理し直せるのが利点で、大学院コア科目への橋渡しとしても機能します。
新聞・雑誌については、日本経済新聞、The Wall Street Journal、Financial Times、The Economistなどを使って理論を現在進行形の現実に当てるための素材で、統計公表・政策判断・市場反応を読み解くリテラシーを身につけるために授業で活用されています。
また院レベルでは
Stokey & Lucas with Prescott『Recursive Methods in Economic Dynamics』
動学計画法の基礎(ベルマン方程式、縮約写像、価値関数反復)から確率動学、最適成長、競争均衡の再帰表現までを厳密に展開する古典です。仮定→作用素→存在・一意性→計算という流れが明快で、後続のマクロ理論・数値解法の“文法”を与えます。応用は最小限でも一般性が高く、のちに扱うRBC、検索・マッチング、不完全市場モデルなどの足場づくりに最適です。
Ljungqvist & Sargent『Recursive Macroeconomic Theory』
RBCから価格硬直性、失業の検索・交渉、信用制約・不完全保険、課税と厚生、政策の時間非整合性まで、現代マクロのコア話題を“再帰形式”で統一的に解き明かすテキストです。概念→モデル→計算例(時に数値)→政策含意という運びで、抽象性と実用性のバランスがよい。学部上級~大学院初年次で「どうモデルを立て、どう比較し、どこを見るか」を身につけるのに最適です。
Walsh『Monetary Theory and Policy』
貨幣・金融の理論と政策運営に特化した標準書。ミクロ基礎づけ(カーヴォ型価格設定等)に立脚したニューケインジアンDSGEを軸に、ルール対裁量、時間非整合性、信用とコミットメント、インフレ目標、ゼロ金利制約や前方ガイダンス、(版によっては)金融摩擦やマクロプルーデンスまでを体系化します。理論→制度設計→実務運営(ターゲティングやフォワードルッキングなルール)をつなぐので、中央銀行の意思決定や政策評価を“モデルの言葉”で語れるようになります。